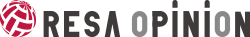【提言】
<人口減少時代の住まいとまちづくり>
・空き家の常識を疑う-空き家が増えているのは人口減少の影響ではない?- 筆者は都市計画、中でも住環境計画を専門としており、自治体の住宅政策に関わることが多 い。そこで最近話題となるのは空き家の増加である。住宅政策としては、公営住宅の整備が 難しい中で、空き家を活用できないか模索することになる。 そのような経緯で空き家の実態を調べるうちに、空き家の常識に疑問をもつようになった。そ れは次の三つだ。 ・一つは、全国の空き家率が 13.5%で、8 戸に 1 戸が空き家という新聞報道である。この数字が 実感に比べて高いのである。 ・セミナーの二つ目は、人口減少により空き家が増えるという解説である。空き家に影響するの は、正確には人口ではなく世帯数である。人口が減少しても世帯数が増えている地域が多い ため、人口減少と空き家の増加は直結していない。 ・三つ目は、人口減少とともに都市も縮小するという指摘である。確かに、人口増加の時代は、 都市は郊外に拡大した。それならば、人口減少により都市が縮小するという説明はわかりや すい。しかし、実態はどうだろうか。以下で検証してみよう。
■空き家率13.5%がもつ意味
この数字は、5年ごとに行われる住宅・土地統計調査によるものだ。直近は平成25年に実施されており、新聞等で報道されたので記憶されている方も多いだろう。この数字は何を意味しているのだろうか。
(1)賃貸住宅の空き家率は18.8%
空き家率には、賃貸アパートの空き室も含まれる。賃貸アパートは、供給過剰と若者世帯の減少により空き室が多い。事実、賃貸住宅総数を母数として空き家率を計算すると、18.8%になる。この数値は、平成20年と平成25年で奇しくも同じだ。この5年間の間に東北大震災があり、住宅を失った人々の需要により、東北地方の賃貸アパートの空き家率は下がった。もし震災がなければ、空き家率は20%に達していたかもしれない。いずれにしても、賃貸アパートの高い空き家率が、全体の空き家率を押し上げていることを確認しておきたい。
(2)持ち家一戸建住宅の空き率は推定8.3%
では、持ち家一戸建の空き家率はどうだろうか。近年、迷惑空き家として注目されているのは、もっぱら一戸建住宅の空き家である。
残念ながら、空き家の分類に「持ち家一戸建」はない。空き家は、調査員が外観から判断する以上、それが賃貸か持ち家かは判断できない。そこで統計上は、「その他」空き家になる。つまり、外観から判断できる「賃貸用」でも「売却用」でも「別荘」でもない、「その他」というわけだ。これには、所有者が亡くなって相続人が住まない例、老人ホームに転居した例などがある。
その中の一戸建住宅が、おおむね「持ち家一戸建」に相当する。それから推定した空き家率は、平成20年で7.0%、平成25年で8.3%と増えている。
(3)大都市では空き家率の誤差が大きい
しかし、大都市では、この数値は実態との乖離が大きい。例えば、東京都北区や豊島区の詳細調査によると、一戸建住宅の空き家率は1~2%である(同時期の住宅土地統計調査の一戸建の空き家率は約8%)。また、千葉県袖ヶ浦市では1.6%で、同時期の統計調査の4.6%の半分以下となっている。なぜ、このように大きな誤差が生じるのだろうか。
(4)抽出調査が誤差の原因ではない
考えられる理由の一つは、この統計調査が1/10~1/20程度の抽出調査のため誤差が生じることである。しかし、誤差が原因であれば、空き家率が高くなることもあれば、低くなることもある。上下両方に誤差がでなければおかしい。しかも、抽出方法は長年の経験で誤差を補正するように洗練されている。このことを踏まえると、「抽出調査だから空き家率が高い」というのは適切ではない。
(5)原因は外観目視による調査の限界
もう一つの原因は、外観目視による調査の限界である。この調査では、調査員は、割り当てられた調査区を事前に調べて状況を把握する。そして、1週間ほどで調査票を各世帯に渡し、その後に訪問して回収する(平成25年よりインターネット回答も可)。
このプロセスにおいて、空き家はどう判定されるのだろうか。外観から明らかに空き家と分かる場合もあるが、一方で、わずかに通電しているが、何回訪問しても応答がないという状況もある。実際は、1~2週間ほど病院に入院したり、海外旅行に行ったりしたのかもしれない。しかし、それは外観からは分からない。調査期間内に居住を確認できなければ、空き家とカウントせざるをえない。
これに対して田舎では、近所に聞くと、「あの家は3日後には帰ってくるよ」「平日は不在が多いが、週末にいるね」などの状況がわかり、そのときに訪問して調査票を渡すことができる。統計調査の空き家率が、大都市ほど誤差が大きいという理由は、以上のような外観目視調査の限界と考えられる。
一方、自治体による実態調査は、空き家に絞った調査である。例えば、水道の閉栓で抽出する例、郵便受けや電気メーターの状況を
基準とする例などがあり、数ケ月から1年間は空き家であることを目安とする。このため、短期間の不在は空き家とカウントしない。この方法のほうが、地域住民の空き家の実感に近いだろう。
つまり、空き家率13.5%は、短期の不在も含まれやすいため、実感より高めの数値であるといえる。
各自治体で空き家政策を検討する際は、ぜひ実態調査をお勧めする。大都市以外ならば、町会・自治会を通した調査が簡便かつ正確だ。空き家の実態を一番よく知っているのは、地域住民だからである。
■統計数値には限界があるという教訓
以上の検証は、統計データには限界があることを教えてくれる。これに関連して、筆者は「政策の数値目標」に疑問をもっているので紹介しよう。
(1)政策の数値目標を疑う
統計調査の限界は、住宅政策の場面でよく経験する。例えば、住宅の耐震化率がある。「耐震性が現行基準を満たしている住宅は80%で、10年計画で90%に引きあげます」という政策目標が語られる。しかし、これは何の数値だろうか。一軒一軒の耐震性を調べるには膨大な手間がかかり、それを統計数値として把握するなど不可能だからだ。
実際は、建築基準法の耐震基準が強化された1981年以降に建築された(確認申請が出された)住宅の数をもって、「耐震性が現行基準を満たしている住宅」としている。しかし、古い住宅でも耐震性が高い住宅は多く、逆に、新しい住宅でも欠陥工事があれば耐震性は劣る。これらをすべて捨象している。しかも、古い住宅は自然に建替えが進むから、10年もたてば「何も政策を実施しなくても」耐震化率は上がることになる。
(2)数値目標を設定できる政策は一部にすぎない
この例で数値が正確なのは、例えば、自治体の補助を受けて耐震改修を実施した住宅数である。これは施策のアウトプットといわれる。しかし、世間や議会は、住宅を地震に強くするという政策の達成度、つまりアウトカムの数値を求める。そこにギャップがある。実は、アウトカムを数値化できる政策は、ほんの一部にすぎない。
図1 政策の数値目標を設定するための二つのハードル
政策の数値目標を示すためには、二つのハードルがある(図1)。一つは、「その政策が数値として表せる」ことであり、もう一つは
「その数値を統計調査で把握できる」ことである。この二つを乗り越えて初めて数値目標を設定できる。しかし、耐震化の例で示した
ように、後者の統計データの把握が大変難しいのである。
他にも、数値化に苦労して変な数値目標を採用した多い。例えば、住宅の省エネルギー化を進める政策を二重サッシュの採用率で代替
したり、コミュニティの活性化を自治会加入率で置き換えたりする。担当者の苦労が伝わってくる。
確認すべきことは、「政策を数値化でき、かつそれを統計データとして把握できる政策は、ごく一部にすぎない」ことである。
この問題を踏まえて、第一に、数値化が難しければ質的目標のままとすべきである。第二に、何らかの事情で数値化せざるを得ない
場合は、必ず資料の中に注釈を付けるべきである。例えば「本数値は、1986年以後に建築された住宅率で代替したもので、実際の耐震
化率とは異なります」と明記する。空き家率も同じだ。「本調査の空き家数は、10月○日から○日までの調査期間に居住が確認できな
かった住宅数を指します」と明記すべきなのである。
■空き家の増加は人口減少の影響ではない
さて、二つ目の疑問を検証してみよう。空き家が増加している理由は何だろうか。
周知のように夫婦のみ世帯や一人暮らしが増えているため、人口が減っても世帯数は増えている地域が多い。世帯数が増えているなら
ば、空き家が増えるのは人口減少の影響とはいえないのではないだろうか。
そこで、人口と世帯数の5年間変化率について地区別に分析してみた。最低千世帯以上になるように地区を合体したもので中学校区程
度が目安である。
図2 常磐線沿線の人口と世帯の増減率 図3 北陸地方A市の例
(1)人口増減率と世帯増減率にはズレがある
図2は、茨城県の常磐線沿線の例である。筆者が茨城県に住んでおり土地勘があるため取り上げた。そして図3は、筆者の実家があ
る北陸地方のA市である。両地域とも人口の減少期に入っている。
①人口減少期でも「発展地域」がある
第1象限は、人口も世帯も増えている地域であり、「発展地域」と名づけた。具体的には、郊外大型ショッピングセンターに行きやす
い近郊住宅地や、駅前再開発が成功してマンションが増えた地区などである。
②人口と世帯の回帰直線は第2象限を通る
第2象限は、人口は減っているが世帯は増えている地域である。将来、世帯数も減る可能性があるため「猶予地域」と名づけた。旧市
街地や郊外住宅地が含まれる。ここに該当する地区が多いため、回帰直線は原点より上側を通る。全体としては、1世帯あたりの家族人
数が減っていることを示している。
③相当数の「衰退地域」がある
第3象限は、人口も世帯も減っている地区であり、「衰退地域」と名づけた。地方都市では、農山村部や昔の新興住宅地の一部が衰退地域になっている。
(2)空き家の増加は人口の重心が移動した結果
重要なことは、人口の減少期にも関わらず発展地域があることだ。その結果、空き家が増加する一方で、住宅が新築され続けている。つまり、人口減少ではなく人口の重心が移動した結果、空き家が増えていると判断できる。
もちろん、その背景には、郊外大型ショッピングセンターの隆盛の一方で、旧市街地を衰退させるという都市政策の見通しの甘さがあることは言うまでもない。
(3)人口と世帯の増減率を地区別に描くことの勧め
同様な分析を東京都世田谷区で行ってみたが、意外な結果であった。人口と世帯の回帰直線が原点を通ったのである。しばらく考えて納得した。大都市では、すでに一人暮らしや夫婦のみ世帯が多く、家族人数が減少する余地は少ない。しかも、世田谷区は、社会増(他地域からの流入)による人口増地域である。人口増はそのまま世帯増に直結するため、両者の増減率が近いものと考えられる。
全国の自治体で、人口と世帯の増減率を描くと面白そうだ。しかし、中学校区程度の地区別に5年間増減率を計算するのは手間がかかる。しかも土地勘がないと、地区区分の妥当性を判断できない。筆者は力不足であり、ぜひ各自治体で描いてみることをお勧めしたい。
その都市の人口の動きがよく分かり、都市政策の参考になるはずだ。
■人口減少は都市を縮小させるのか
三つ目の疑問に入ろう。人口減少は都市を縮小させるのだろうか。
(1)都市の縮小までに3つのステップがある
一つ目のステップは、人口減少が世帯数の減少につながることである。これは、時間差があるが10~15年後に世帯数も減少に向かうと予測されている。
二つ目は、世帯数の減少が住宅数の減少につながることである。しかし、現時点では空き家の増加となっており、住宅の滅失にはつながっていない。
三つ目は、住宅数が減少したと仮定して、それが都市の縮小につながることである。しかし、これは実現しそうにない。都市を縮小するように整然と住宅が滅失することはなく、単に「歯抜けが生じる」だけだ。つまり、住宅地としては存続しており、上下水道や道路などの都市インフラを撤退することはできない。
すなわち、上記の第2段階と第3段階に飛躍があり、人口減少が自然に都市を縮小させるとは考えられないのである。
(2)都市政策の目標として多極型コンバクトシティ
では、なぜ都市の縮小が話題になるのか。それは、現状の延長にあるのではなく、目指すべき目標像だからである。人口減少により税収が減る中で、上下水道、電気、ガス、学校等の公共施設の維持は困難になる。これによる財政破綻を避けるために、都市の縮小が必須になる。
図4 多極型コンパクトシティ
筆者が描く目標像は、「多極型コンパクトシティ」(図4)である。都市のコンパクト化の中心地は一つではない。複数の中心地ができ、それに向けて都市を集約していく。この場合の中心地とは、「歩いて暮らせる街」のことだ。生活に必要な機能が身近にあり、自家用車に頼らなくても暮らせる街である。その候補として、中心市街地はもとより、大きな郊外団地も有力だ。戸数が多いため、店舗、福祉サービス等を成立させやすいからだ。
もちろん、多極型コンパクトシティの実現は、政治的には容易ではない。中心地から外れた住民から「我々を見捨てるのか」という批判を浴びるからだ。確かに、学校は統廃合され、福祉サービスも充実が難しくなる。しかし、スクールバスを運営したり、老後は中心地に気楽に引っ越したりする選択が確立すれば、それらの欠点を補える。そうすれば、人口減少を逆手にとって、2倍3倍の広い敷地面積をもつ「緑とゆとりの田園住宅地」へと発展・変貌できるはずだ。
多極型コンパクトシティとは、非中心地を見捨てるのではなく、中心市街地、郊外団地、田園住宅地、集落の各々が、明確に異なる特色をもったまちづくりである。
多極型コンパクトシティの実現に向けて、郊外の開発規制、中心地の活性化と課税強化、その税収増による撤退地域からの住み替え支援、等が課題になる。いずれも痛みを伴う施策だが、それに取り組む自治体が人口減少時代の勝ち組になるだろう。
■おわりに-地方分権の真価が問われる
人口減少時代の到来は、発展地域と衰退地域の二極分化を生み出し、同時に、自治体間にも格差を生み出す。それは、自治体間競争を背景とした地方分権の始まりを意味する。
2000年に地方分権一括法が施行された。筆者の身近な政策では、建築基準法の運用が注目されている。とくに、建物の使い方は時代や地域で異なり、法律に定めのない用途が登場する。最近では、民泊やシェアハウスが話題である。それらを法律上のどの用途とみなすのか。その判断が建築規制のあり方を左右する。
地方分権一括法により、建築基準法の運用は、機関委任事務から自治事務に変わり、自治体の裁量が拡大した。これを生かして福島県や愛知県は、一戸建住宅を転用したグループホームを「住宅」のままと用途判断した。空き家の増加の一方で、福祉施設が不足している現状を踏まえると適切な判断といえる。
しかし、国は、2013年9月に事業者が運営する多人数居住を「寄宿舎」とみなすという技術的助言を示した。その背景には、劣悪な脱法ハウスが横行し、それを規制する必要があった。しかし、不健全な脱法ハウスと良心的な多人数居住の区別は難しい。結局、健全なグループホームやシェアハウスも一律に規制され、空き家活用に打撃となった。
この問題を解決するには、自治体が条例等によって用途判断を明確にする方法がある。もちろん、建築基準そのものの緩和はできない。しかし、法律や政令に定めがない新しい使い方について、その用途を判断するのは特定行政庁だ。これを踏まえて、健全な多人数居住の範囲を定め、その空き家活用は、寄宿舎ではなく住宅のままとするわけだ。例えば、6人以下かつ一人当たり15㎡以上の空き家活用を住宅扱いとする案がある。
建築における安全と活用のバランスを判断できるのは、行政職員ではない。職員は、万一の事故を考えると安全側で判断せざるを得ないからだ。その判断は政治の役割である。用途判断を明確にする条例等があれば、空き家活用は格段に進めやすくなる。
自治体間競争の試金石の一つとして、まずは建築基準法の運用について地方独自の扱いを競争してみてはどうだろうか。