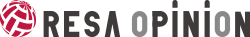【論評】
<個人向け不動産融資への取組み姿勢を再考する>
・セミナーの日銀による低金利政策の影響を受け、金融機関は総じて収益力低下の状態にあるが、その中で不動産融資は収益を確保できる唯一の運用手段でもある。しかし、昨年来様々な問題融資が発覚し、取扱いにブレーキがかかっている情況だが、金融機関経営にとって「個人向け不動産融資」は問題なのか否か検証してみたい。
■不動産融資傾注の実情
日本銀行が公表した「金融システムレポート2019年4月」では、不動産業向け貸出の対GDP比率が過熱状態にあると示された。銀行貸出はここ1、2年減少傾向にあるが貸出金全体に占める不動産業者向けの残高は依然高い状態にある。地方銀行に関しては、自己資本比率が低い銀行ほど貸出金に占める不動産向貸出比率が高い傾向にあるという特徴もある。
バブル期のような「更に地価は上がる」という成長期待による加熱状態とは言えないが、REITや不動産ファンド、個人の賃貸業向け等賃貸収入目的の中長期投資向け貸出が中心で、中長期的には空室増加や賃料下落というリスクに晒されている。将来の物件需要(=人口減少と世帯数減少)に対しては過大投資とも想定され、相当のリスクを抱えている可能性は否めない。
出典:日本銀行 金融システムレポート概要編 2019年4月
■個人向け不動産融資の実情
公表ベースで金融機関の扱う個人向け住宅ローンの中には、純粋個人の投資用物件(アパート等)に対する融資残高も含まれるケースも多いが、住宅支援機構が毎年公表している、金融機関の住宅ローン残高は2018年12月末時点で196兆円となっている。1990年と比較すると60%相当増加している。統計によると年間20兆円程度の新規取扱いが続いているが、伸び率を考えると住宅金融専門機関から銀行、信金、労金、農協へ貸出がシフトするとともに、金融機関間の借換えによるものが多いと想定される。
【図表:住宅ローン貸出残高(期末)】
新規住宅の着工戸数推移はリーマンショック後の2010以降年間100万戸を下回る状況が続いているが、新規着工の内でローンを利用する比率は5~7割程度、単価20百万円と想定すると、年間10兆円程度の取扱いと推測できる。また、今後の着工戸数の予想を勘案すると住
宅関連融資は減少の一途になるのではないか。【図表:新設住宅着工戸数の実績と予測結果】
一方、地方銀行64行の2010年から2018年の間の住宅ローン残高の伸び率と業務純益の伸び率を比較すると、住宅ローンの伸び率が高い程、業務純益の伸び率も高まる(総じてマイナスの状態ではあるが…)という傾向もみられることから、低金利下、中小企業貸出が伸びない中、収益の柱として個人向け住宅関連貸出に注力している実態が分かる。 【図表;住宅ローン残高伸び率と業務純益伸び率の相関】
〔住宅ローン残高伸び率と業務純益伸び率の相関〕
※一般社団法人地方銀行協会 提供 加盟銀行財務情報を使用し筆者が作成
■金融機関が抱える不動産関連リスク
バブル期は不動産市場価格が高騰する中、大型の不動産取引業者向け貸出が主体となり、土地価格暴落により不良債権化が顕在化したが、現在の不動産融資は中長期投資向けが主である一方、中小企業や個人など損失の吸収力が低い貸出先の比重が高いことから、価格、価値下落による金融機関本体のリスク許容度は低くなっている=直接的に損失負担となる可能性を含んでいる。
前出の残高と収益の相関グラフからも分かる通り、不動産向け融資で問題をおこした「スルガ銀行」は、不祥事による対象融資を損失処理することで残高は減少し、業務純益は大幅に減少していることが分かる。他の金融機関もリスクが顕在化することで同様の状態になる可能性が極めて高いと思われる。
また、地域金融機関はJ-REITや私募REITなどの不動産ファンド向け出資を増やしているが、エクイティという投資対象の性質から考えると、不動産市況の悪化局面では貸出よりも価値が毀損する可能性が極めて高いことも問題と考えられる。
■実需に合致した融資を考える
国内マーケットの不動産需要の中で、ある意味ベースとなるであろう個人を対象とする住宅向け融資を考えるならば、高齢化の進展と社会保障制度の課題という社会問題から、持ち家比率の高い高齢者が保有する住宅資産を活用した事業モデルは検討に値するのではないか。
バブル期、資産価値が上がるという前提で、住宅価値を評価、極度額を設定して利用できることを謳った不動産担保融資の一つとして、高齢者向けの「リバースモゲージ」を取り扱う金融機関が多かったが、①土地価格の下落による価値評価額の減価、②金利上昇による支払い負担の増加、③融資想定期間を超え借主が生存し物件を処分しても債務が残ってしまう課題が顕在化し、当該3大リスクを回避できなければ運用は困難ということで、以後、取扱いは減っていた。
しかし、近年、その流れが変わりつつある。東京スター銀行が積極的に「リバースモゲージ」を取扱っているのは承知のことだが、住宅支援機構が提供する「住宅融資保険」を利用した「リバース型ローン」=「リ・バース60」を取扱う金融機関も出てきている。また、不動産処分信託を活用したリバース型ローンを扱う金融機関もあるが、地銀トップの横浜銀行も本年4月にリバースモゲージの取扱いを開始したと公表している。
最近の不動産価格の推移を見る限り、急上昇とはいかないが主要都市では上昇に転じている情況下、物件の将来価値を意識したリバース型ローン商品の場合、最終処理時点に想定されるリスクをどのように考えるかがポイントになると思われる。
住宅支援機構が提供する「住宅融資保険」に関しては、最終的には対象となる物件を処分し債務が残る場合は相続人が負担するという仕組みとなっているが、前述した金融機関のモデルも総じて同じような扱いであり、関係者が最終負担することになっているのではないか。つまり、金融機関も含め関係者にとって最終的な債務処理の負担が残るものと想定される。
融資関連商品を考える場合、入口段階の扱いよりも最終処理の仕組み=利用者負担を最大限抑えることができる仕組みを考えることが重要であり、当該商品を普及させるには、ノンリコース型ファイナンスを前提にした仕組みを体系化することがポイントになるのではないだろうか。すなわち、わが国ではなかなか普及しない「ノンリコース型ファイナンス」を「適正な住宅資産の将来価値評価」と「住宅資産の再利用マーケット構築」という観点からビジネスモデル化することが重要になるのではないだろうか。